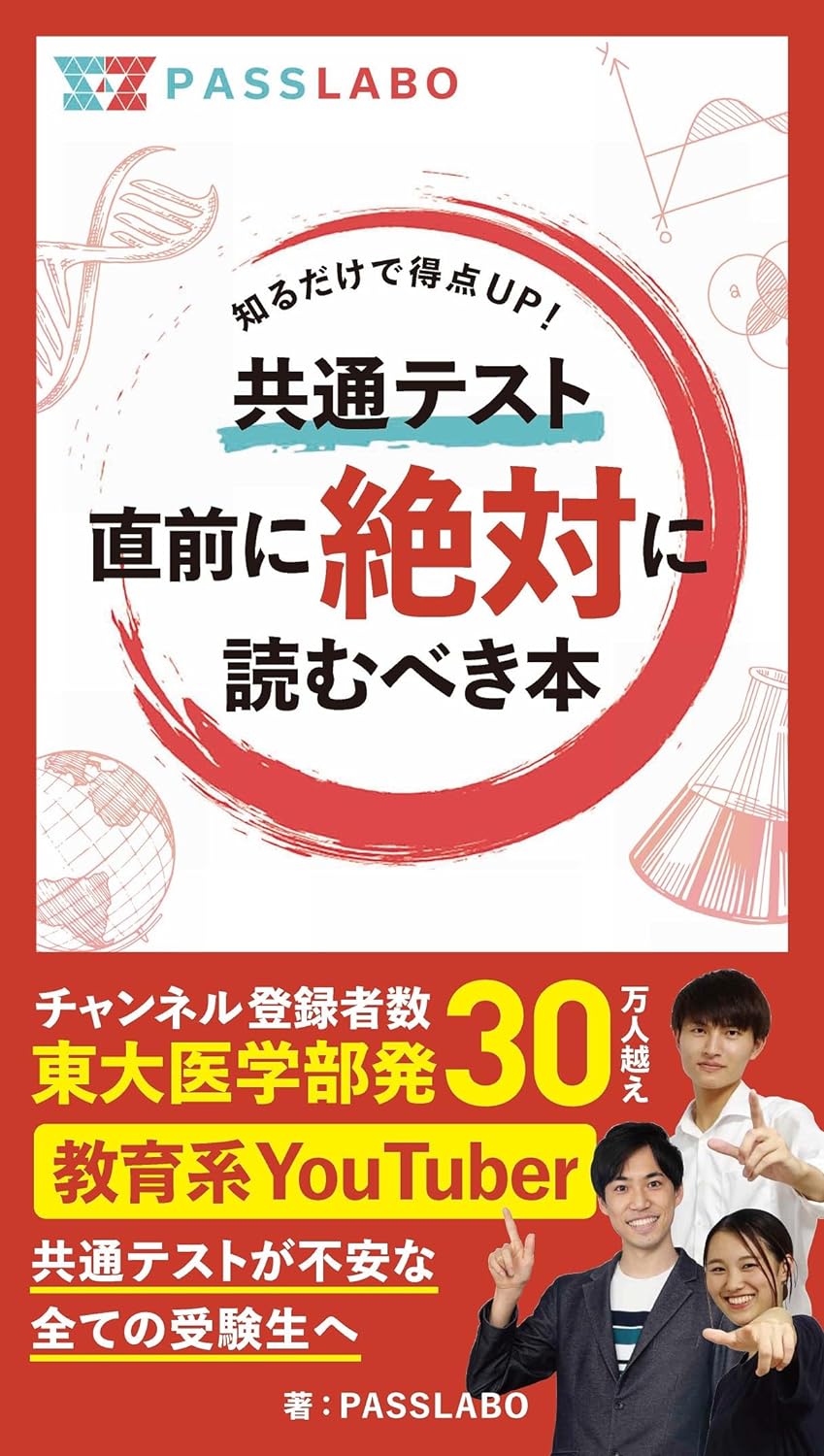第13回 現代文の語彙の学習法・④漢字の意味から語彙を増やす
前回は、「普遍‐特殊」「主観‐客観」「絶対‐相対」という3組の対義語を例にとり、言
葉どうしの関係を理解しながら語彙の学習を進めることの重要性についてお話ししました
。言葉はそれぞれが独立して存在するのではなく、お互いに関連しあって一つの言葉の世
界を構成しています。中でも対義語と同義語は必ず押さえてください。また、「普遍-客
観-絶対」と「特殊-主観-相対」という組合せは、評論文の読解においてきわめて重要
ですので、意味を理解したうえで頭に入れてください。
さて、評論文で用いられる術語はおおむね漢字の熟語です。ですから、漢字の意味の理
解が語彙力の強化に直結します。そこで、今回は漢字の意味に注目した語彙の学習法につ
いてお話したいと思います。
(なお、欧米語由来のカタカナ語もありますが、これは別途覚えましょう。『新ゴロゴ現
代文〈語彙・テーマ〉では、第7章で必須のカタカナ語128語を整理していますので、活用
してください。)
記事でたびたび出てくる「抽象」ですが、この語は「抽」と「象」という2つの漢字か
ら成り立っています。まず、「抽」は〈取り出す〉という意味です。「抽選」「抽出」と
いった熟語もありますね。次に、「象」の意味は〈姿・形〉です。2つを合わせると、〈
形を取り出す〉という意味になります。
では、どのような〈形を取り出す〉のでしょうか? イチゴ・みかん・りんごを抽象化
すると〈果物〉、ジャガイモ・レタス・トマトを抽象化すると〈野菜〉であるように、共
通する要素を取り出すわけです。こうして、「抽象」は〈具体的なものから共通する要素
を取り出して、頭の中でまとめること〉という意味になります。
ここで、「象」という漢字に注目してください。この字を用いた術語には、そのほか「
象徴」「現象」などがあります。「徴」は〈目印〉という意味ですので、「象徴」で目印
となる姿・形です。「ハトは平和の象徴」と言うように、「平和」という目に見えない観
念を、「ハト」という具体的な事物で表わす。それが「象徴」ということになります。ま
た、「現」は〈物の現われ〉という意味ですので、「現象」で〈現実に知覚できる姿・形
の現われ〉です。
表音文字であるひらがなやカタカナと違って、漢字は表意文字としてその文字が意味を
表わしています。ですから、漢字の意味に注目すると術語の意味も理解しやすくなります
し、また、「抽象」「象徴」「現象」のように言葉の世界が広がっていきます。漢字学習
は現代文読解の土台となるものですから、語彙学習と並行して進めていくとより効果的で
す。
以上、4回にわたって現代文の語彙の学習法についてお話してきました。古文単語や英
単語を覚えるように、評論文で用いられる術語も覚えていってください。
次回からは、現代文で扱われるテーマの学習についてお話していきます。